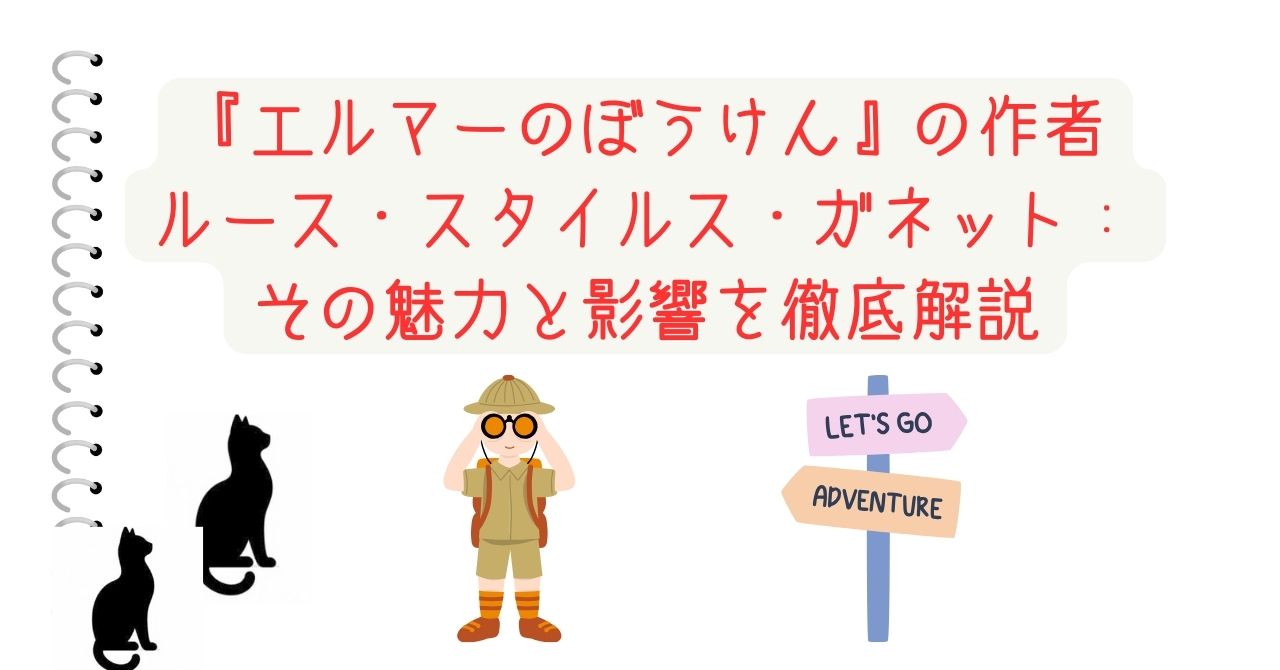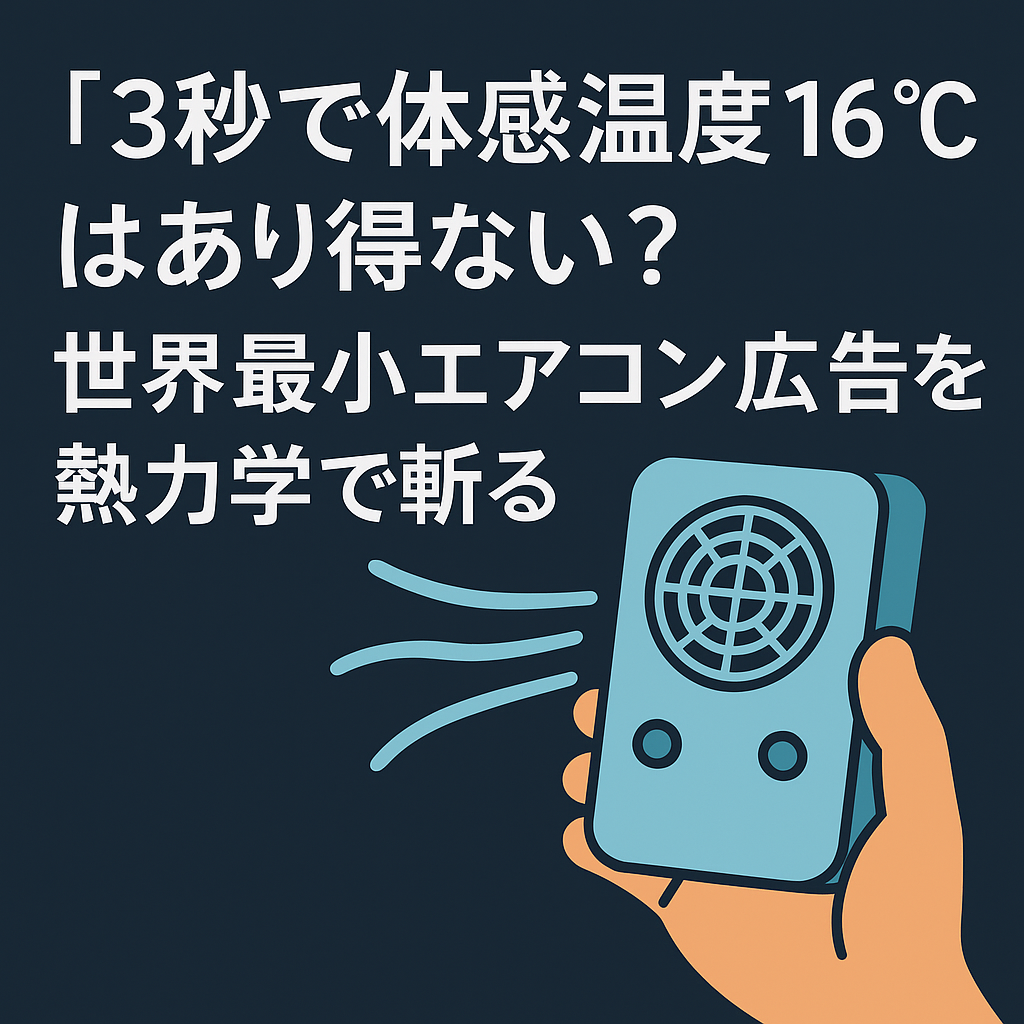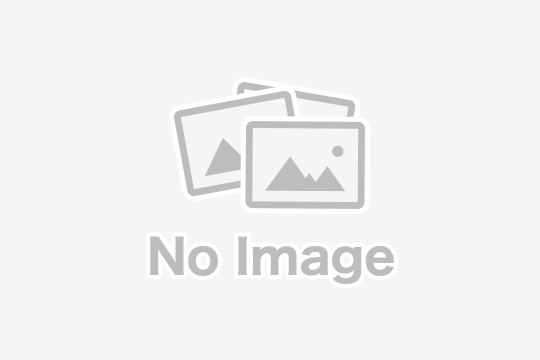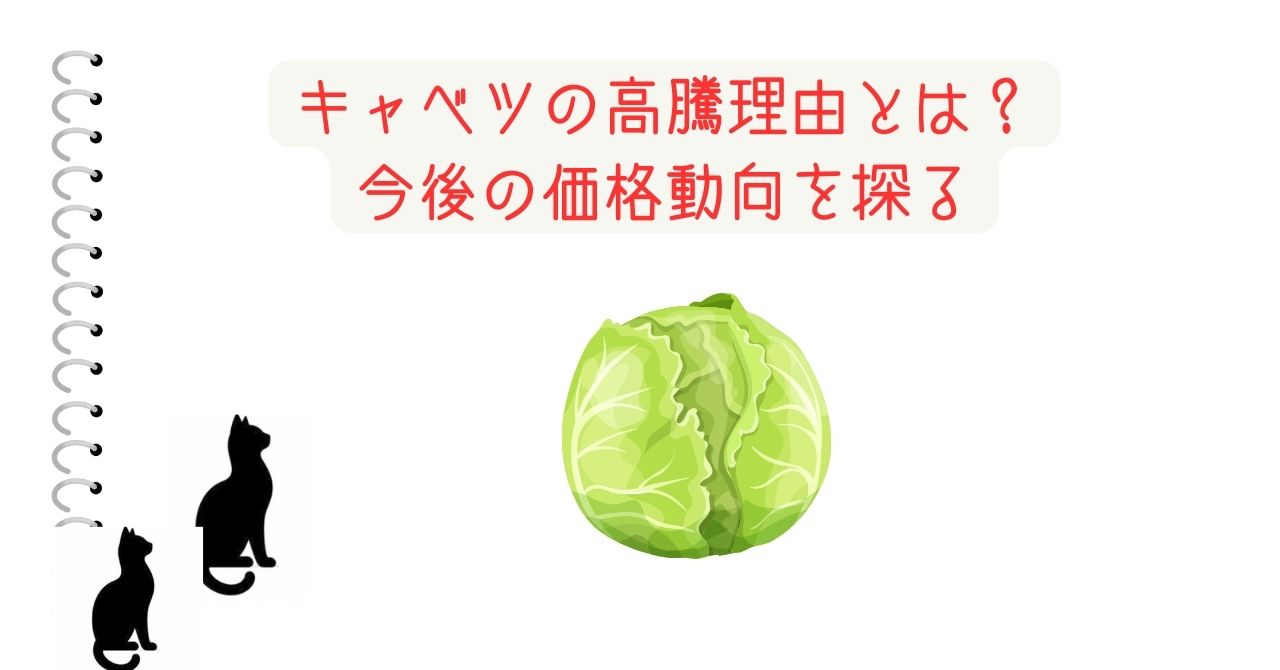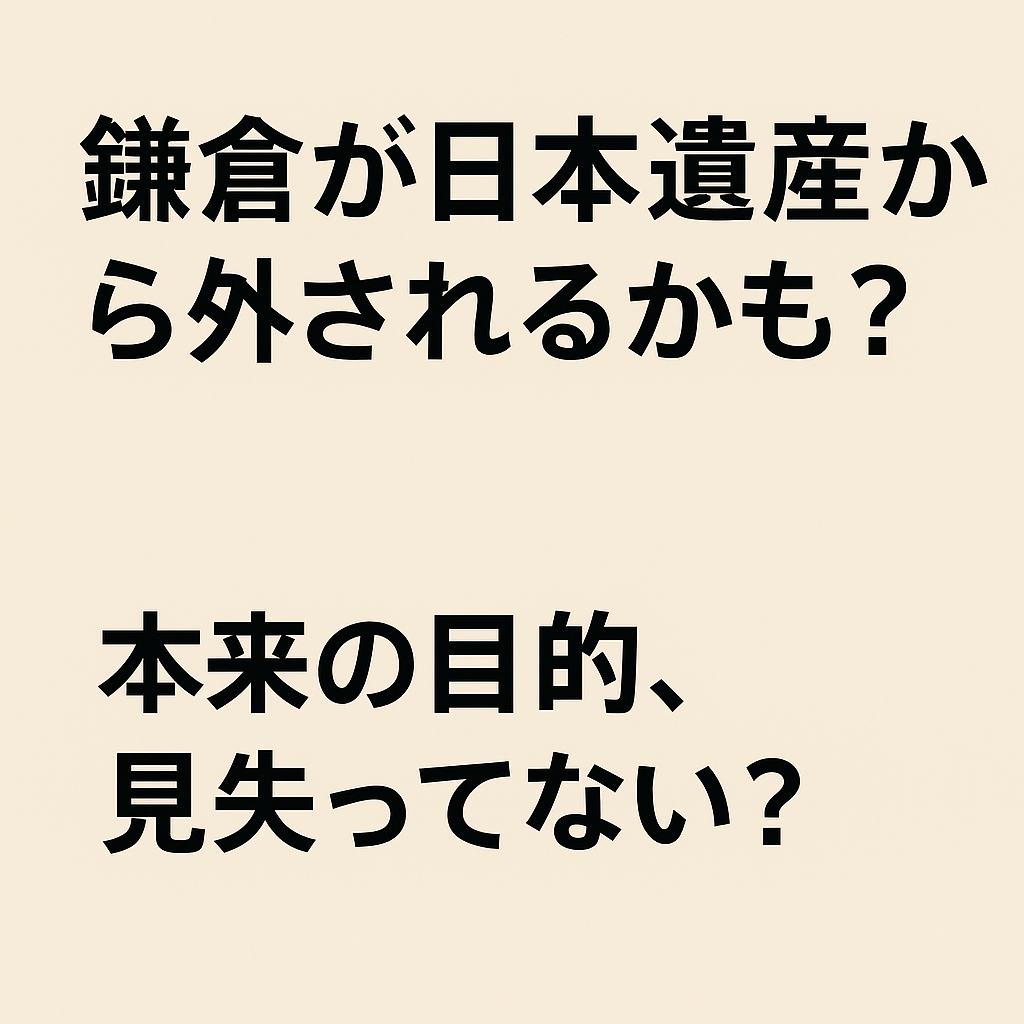無銭飲食でも不起訴?その理由を解説します
先日、飲食店で発生した「無銭飲食事件」がニュースになっていました。
男性が居酒屋で約5,000円分の料理とお酒を注文し、支払いをせずに店を出てしまったというものです。
さらに別の店では17万円あまりの飲食もしていたとのこと。しかし驚くべきことに、この男性は「不起訴」となったのです。
なぜ不起訴になるのか?
不起訴とは、検察が「裁判にかけても有罪にできる見込みがない」と判断した場合に下される処分です。
今回のケースで考えられる理由を整理すると以下の通りです。
- ① 故意の立証が難しい
無銭飲食を「詐欺罪」として立件するには、
「最初から支払う意思がなかった」ことを証明しなければなりません。
しかし本人が「迎えに行くつもりだった」「支払う意思はあった」と言い張ると、
防犯カメラ映像だけでは立証が難しいのです。 - ② 被害額が比較的少額
初回の被害額は5,160円。
検察は社会的影響や訴訟コストも考慮するため、少額事件は不起訴になりやすい傾向があります。 - ③ 証拠の評価
防犯カメラは「飲食して店を出た事実」を示すものの、
「最初から払う気がなかった」ことの証明には直結しません。
そのため決め手に欠けるのです。 - ④ 常習性の証明不足
17万円の飲食も報じられましたが、
それも「たまたま支払い能力がなかった」と言い逃れされると、
常習犯として立件するのは難しい場合があります。
「支払う意思」が判断基準になる
無銭飲食の立件で一番のハードルは、この「支払う意思」の有無です。
法律上は「最初から払うつもりがなかった」と立証できなければ詐欺罪にはなりません。
逆にいえば、「払うつもりだった」と主張されれば、それを否定する証拠が必要なのです。
このため、「気がなかった」と言い張られると不起訴になりやすいのが現実です。
ただし常習性があったり、明らかな嘘(「財布を取りに行く」と言って戻らない等)があれば、
故意を認定できる場合もあります。
要は「支払う意思が最初からなかった」と検察官に確信させるだけの証拠が揃うかどうかが分かれ目なのです。
被害者にとっての問題点
店主からすれば、防犯カメラもあり被害も明らかなのに不起訴というのは納得しづらいですよね。
実際には刑事事件での立証が難しいため、民事で「代金の支払い請求」をするしかありません。
しかし相手に資力がなければ回収は困難です。
検察審査会という手段
今回の店主は「不起訴処分」に不服を申し立て、検察審査会に申し立てを行ったそうです。
審査会が「不起訴は不当」と判断すれば、再び検察が捜査・起訴する可能性もあります。
ただし金額の少なさや立証の難しさを考えると、再起訴のハードルは依然高いのが現実です。
飲食店側ができる対策
「不起訴になってしまうなら、店はどう守ればいいのか?」という疑問が出てきます。
現実的な対策としては次のようなものがあります。
- 初めての客や不審な客には前払い制やキャッシュオン方式を導入する
- 高額注文が出た際には事前に支払い確認をする
- 被害が出たら必ず警察に通報し記録を残す
- 近隣店舗と情報共有し、常習犯を把握しておく
完全に防ぐことは難しいですが、「逃げられにくい仕組み」を作ることが抑止力につながります。
まとめ
無銭飲食が不起訴になる背景には、
「支払う意思がなかったことの立証の難しさ」や、
「金額の少なさ」があります。
被害者にとっては納得しづらいですが、法律上は「だまし取る意思」を証明できなければ詐欺にはならないのです。
そのため店側としては、防犯カメラに加えて支払い確認の仕組みを整えておくことが重要です。
今回のケースは、法律の限界と現場の不安のギャップを浮き彫りにした事例だと言えるでしょう。