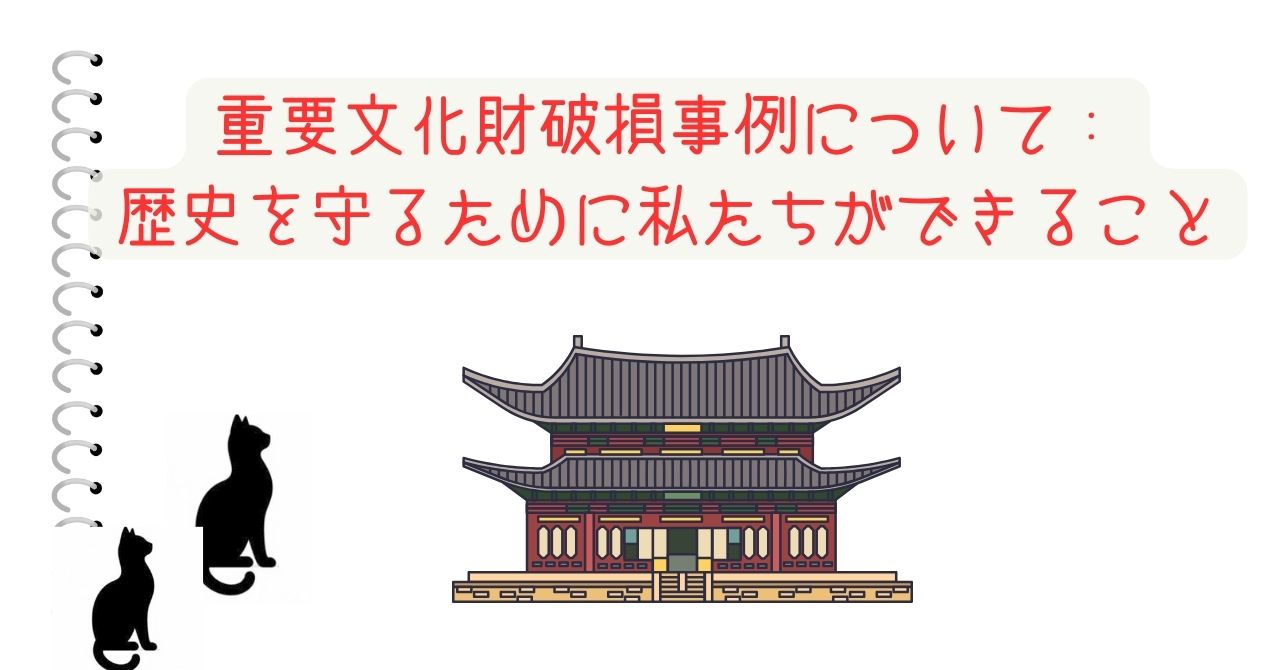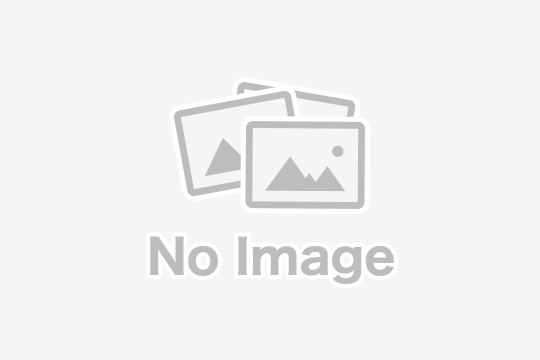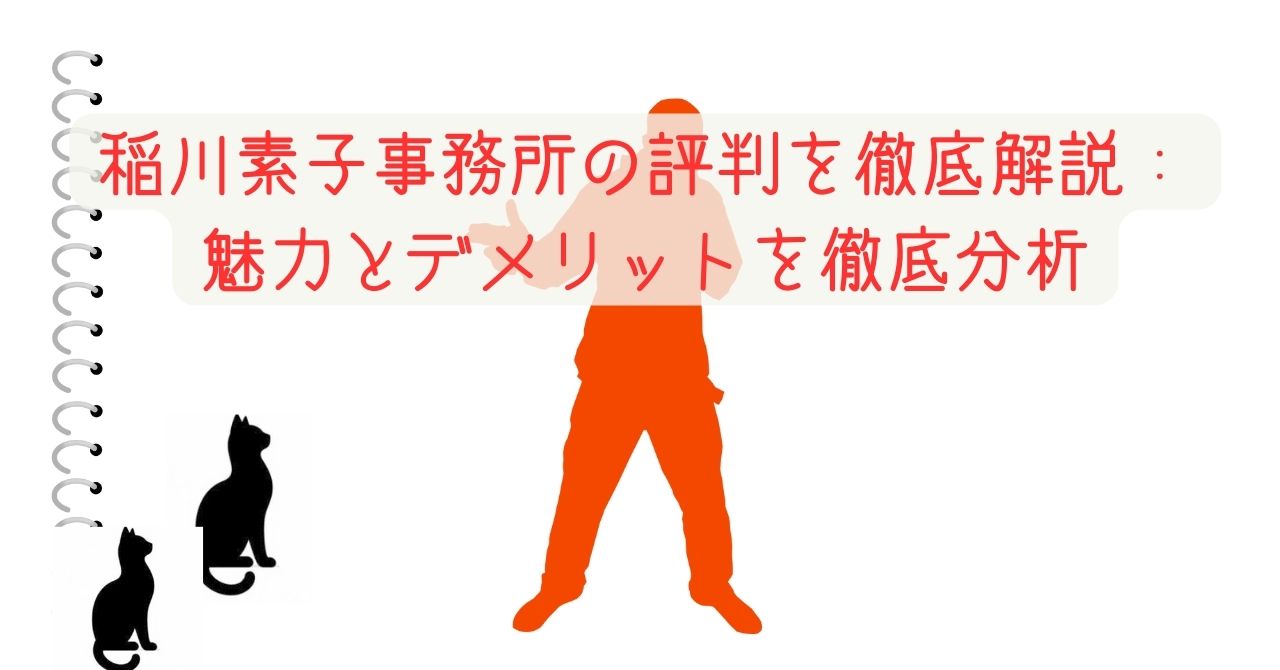子どものスマホ使用時間はどのくらいが適切?年齢別の目安と家庭でできる工夫
「子どもにスマホをどれくらい使わせていいのか…」
親として悩む場面、多いですよね。
勉強にも役立つ一方で、ゲームやSNSに夢中になると健康や生活習慣に悪影響を及ぼすのも事実。
この記事では、子どものスマホ使用時間の目安や年齢別の推奨時間、そして家庭でできる具体的な対策をわかりやすく解説します。
(関連記事)豊明市のスマホ1日2時間条例とは?全国初の取り組みと世界の制限例を解説
(関連記事)スマホ依存の対策はどうすればいい?今日からできる工夫を紹介P
なぜ「子どものスマホ使用時間」が問題になるのか?
子どもにとってスマホは、便利で楽しい存在です。
しかし長時間の利用にはリスクがあります。
- 睡眠不足:夜遅くまでスマホを触って寝不足になる
- 学力低下:勉強時間や読書時間が減る
- 視力への影響:ブルーライトによる眼精疲労
- 依存傾向:SNSやゲームにのめり込みやすい
- コミュニケーション不足:家族との会話が減る
大人でも依存しやすいのに、自己管理能力が育ちきっていない子どもにはさらに影響が大きいのです。
世界の専門機関が示す「スマホ使用時間の目安」
各国の医療機関や研究機関では、子どものスクリーンタイム(スマホやタブレット、ゲームを含む)に目安を出しています。
- WHO(世界保健機関)
- 2歳未満:画面時間ゼロ
- 2〜5歳:1日1時間未満
- 日本小児科医会
- 就学前:1日30分〜1時間が望ましい
- 小学生:1〜2時間以内が目安
- 中高生:生活リズムを崩さない範囲で2時間程度
- アメリカ小児科学会
- 2〜5歳:1時間以内
- 学齢期:宿題や睡眠を優先しつつ、保護者がルールを決める
つまり「年齢が低いほど短く」「成長しても2時間前後が上限」というのが世界的な共通認識です。
年齢別のスマホ使用時間の目安(まとめ)
- 未就学児(〜6歳):1時間以内
- 小学生:1〜2時間以内
- 中学生:2時間程度まで
- 高校生:学業・睡眠を優先にした上で2〜3時間程度
ただし「何に使うか」で意味は大きく変わります。
勉強や調べ物なら多少長くてもOKですが、ゲームやSNSだけで数時間は要注意です。
日本の自治体の動き:豊明市の条例
2025年、愛知県豊明市が「市民のスマホ使用は1日2時間以内を目安」とする条例案を提出しました。
小学生は21時まで、中学生以上は22時まで、という時間の区切りも盛り込まれています。
強制力はなく、あくまで「努力目標」ですが、子どものスマホ使用をめぐる社会的関心の高さを示す事例です。
家庭でできる「スマホ使用時間の工夫」
1. 家族でルールを決める
親が一方的に「ダメ!」と言うより、子どもと一緒にルールを作る方が守られやすいです。
「ゲームは1日1時間」「夜9時以降は使わない」など、納得できる基準を一緒に決めましょう。
2. 使用時間を見える化
iPhoneなら「スクリーンタイム」、Androidなら「デジタルウェルビーイング」で利用時間を確認できます。
「今日は1時間半だったね」と親子で一緒にチェックするだけで意識が変わります。
3. 寝室に持ち込まない
寝る前のスマホは睡眠を妨げます。
リビングで充電するルールにすると、夜更かし防止に効果大。
4. 勉強と遊びを分ける
学習アプリや調べ物は「学習時間」、SNSやゲームは「余暇時間」と区別すると、子どもも納得しやすいです。
5. 親も一緒に守る
「子どもにだけ制限」は説得力がありません。
大人も一緒に利用を減らす姿勢を見せることで、子どもも自然に従いやすくなります。
スマホをやめられないときの工夫
- モノクロモードに設定:色が消えると刺激が減り、面白さが薄れる
- アプリの削除やフォルダ整理:アクセスを一手間増やすだけで触る回数が減る
- アナログな代替:時計・本・メモ帳をスマホ代わりに用意する
- アクティビティで置き換える:外遊びや運動、読書に時間を置き換える
「やめなさい」より「やめやすい環境づくり」がポイントです。
親の悩みに寄り添う考え方
子どもがスマホを長時間使っていると不安になりますよね。
でも「依存かどうか」を見極めるサインもあります。
- スマホを取り上げると激しく怒る
- 食事中や入浴中も触りたがる
- 宿題や睡眠が極端に削られている
こうした場合は専門家の相談も検討しましょう。
小児科や教育相談窓口でも対応してくれます。
まとめ:子どもと一緒に「スマホの使い方」を育てる
子どものスマホ使用時間は、年齢や用途によって適切な範囲が異なります。
一般的には「1〜2時間程度」が目安ですが、重要なのは時間だけでなく中身。
- 学習や調べ物なら有効に活用できる
- 夜更かしやゲームのしすぎは避ける
- 家庭ごとにルールを決め、親も一緒に守る
スマホは完全に禁止するのではなく、正しく付き合う力を育てることが大切です。
親子で「どんな使い方なら安心か」を話し合いながら、健全なスマホ習慣をつくっていきましょう。
豊明市のスマホ1日2時間条例とは?全国初の取り組みと世界の制限例を解説