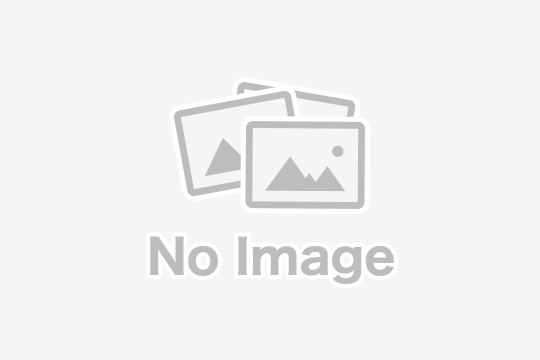堀ちえみさんへの誹謗中傷事件、偽計業務妨害は“意図”か“結果”か?」
事件の概要
堀ちえみさんは2019年に舌がんを公表し、闘病と芸能活動を続けてきました。
そのブログに対して、中島早苗被告は2023年から2025年にかけて「うそ八百」「顔がゆがんでいる」などの誹謗中傷を約1万6000件投稿したとされています。
東京地裁は2025年8月、「被告の行為は社会的に許されないほど悪質であり、堀さんの業務を妨害した」として懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
争点となった「意図」
裁判で注目されたのは、偽計業務妨害罪の成立要件です。
この罪は「虚偽や策略を用いて、他人の業務を妨害する意図」が必要とされています。
被告は誹謗中傷の事実自体は認めつつも、「妨害する意図はなかった」と主張しました。
つまり、「意図」があったかどうかが大きな争点となったのです。
結果と意図の乖離
一方で、実際には堀さんの精神的負担や活動への影響は明らかでした。
長期間にわたる大量の投稿がブログ運営に支障を与えたことも否定できません。
このように「意図はなかった」と被告が主張しても、結果として業務が妨害されている以上、裁判所は責任を認定せざるを得ない状況となります。
「意図」か「結果」か
刑法は従来、故意や意図の有無を重視してきました。
しかし実際の運用では、本人の主張よりも客観的な状況や結果から意図を推認するケースが多く見られます。
「そんなつもりはなかった」「同意があったと思った」など、主観だけでは真実が分からないからです。
そのため今回の事件は、「意図を要件とする法律」と「結果を重視せざるを得ない現実」のギャップを浮き彫りにしました。
例えば交通事故を考えると分かりやすいでしょう。
ちょっとした不注意で事故を起こした場合と、飲酒や危険運転で事故を起こした場合。
結果として被害が出る点は同じですが、悪質性や責任の重さは明らかに異なります。
この違いをどう評価するかは「量刑」で調整するのが現実的です。
つまり、責任を問う基準は結果に置きつつ、意図や態様は刑の重さで考慮するという考え方です。
同じことは医療過誤でも言えます。
医師に悪意がなくても、結果として患者に重大な被害を与えた場合、責任が問われるのは当然です。
また職場でのハラスメントも、「冗談のつもりだった」「励ましのつもりだった」と言っても、結果として相手が精神的被害を受けていれば問題になります。
このように、意図よりも結果を重視する考え方は多くの分野で妥当性を持っています。
海外との比較
海外では、誹謗中傷や差別発言に対して「意図」よりも「結果」を重視する傾向が強い国があります。
たとえば欧州の一部では、SNSや公の場での中傷発言は、被害が生じた時点で処罰の対象となります。
発言者が「そんなつもりではなかった」と弁明しても、被害者の権利が優先されるのです。
これは表現の自由とのバランスを取りながらも、「被害がある以上、責任を問うべき」という考え方に基づいています。
一方で日本では、偽計業務妨害罪のように「意図の有無」が要件とされるケースが多く、
被告の主張次第で争点がずれ込むことも少なくありません。
今回の堀ちえみさんの事件は、その典型的な事例だといえるでしょう。
今後の課題
結果を基準にすれば、被害者救済や再発防止につながる一方、軽微な不注意まで重く処罰されるリスクもあります。
現実的には、まず結果を重視して責任を認定し、意図や悪質性は量刑の段階で考慮するという仕組みが妥当といえるでしょう。
今回の事件は、「意図」と「結果」のどちらに重点を置くべきかを社会全体に問いかける事例となっています。