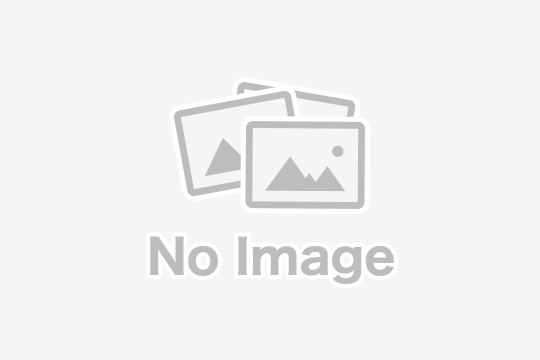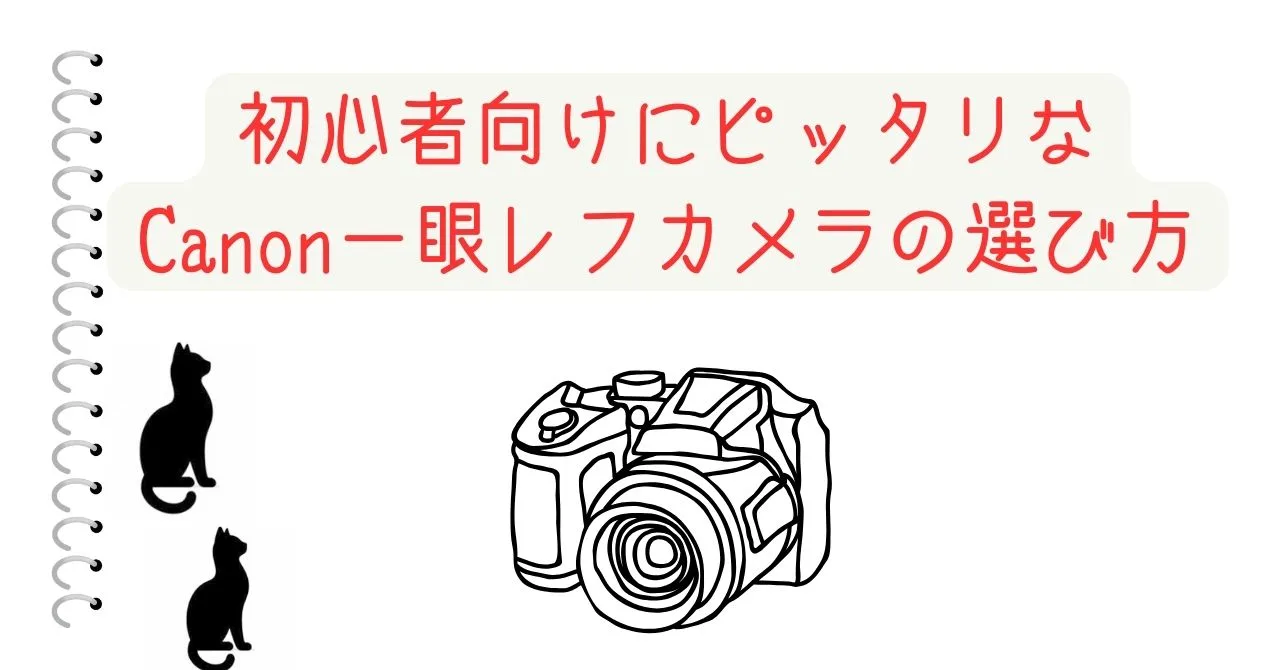カメラレンズのピントリングがベタつく本当の理由と対策
古いレンズを触ると「ピントリングがベタベタする…」という経験、ありますよね。ネットでは「加水分解のせい」と片付けられがちですが、実際にはもっと複雑です。この記事では、疑問に答える形でわかりやすく整理してみます。
ピントリングのゴムの配合は?
実際のリングはひとつのゴムではなく、いくつかの合成ゴムをブレンドしています。
- EPDM(エチレンプロピレンゴム):紫外線やオゾンに強い。耐久性はあるが硬め。
- NBR(ニトリルゴム):油や皮脂に強い。グリス汚れに耐えるため混ぜられる。
- ポリウレタン(PU)系:柔らかくグリップ感が良いが、水分を吸って分解しやすい。
- カーボンブラック:黒い色と耐摩耗性を与える補強材。
なぜベタつくの?
ベタつきには大きく2つの原因があります。
- 可塑剤のにじみ出し
ゴムを柔らかくするために加えた油分(可塑剤)が時間とともに表面に出てくる。触ると油っぽいベタベタ感が出る。 - ポリウレタンの加水分解
水分を吸収して分子が切れ、低分子のドロドロ物質になる。Zuiko Digital 14-54 の「バターみたいに溶ける」現象はこれ。
加水分解だけじゃない
ネットでは「加水分解で終わり」と言われがちですが、実際は可塑剤のにじみ出しも大きな要因です。つまり、ベタつき=加水分解+可塑剤のブリードアウトの複合作用なんです。
可塑剤って何が使われてるの?
昔はフタル酸エステル系(DEHPなど)が主流でした。これはゴムやプラスチックと相性がよく、にじみにくかったのですが、健康や環境への懸念から2000年代以降は規制され、今はほとんど使われていません。
代わりに使われているのが、
- アジピン酸エステル系:安全性は高いが相溶性が弱くにじみやすい。
- シトレート系:食品用途にも使える安全性。ただし揮発やブリードしやすい。
- ポリエステル系可塑剤:にじみにくいが高価。
つまり、規制で安全性は上がったものの「むしろにじみやすい」配合になっていることもあるのです。
具体例で見てみる
- Canon EF-S 18-135mm
表面がベタつく程度。無水エタノールや台所洗剤で拭き取ればベトつきはなくなる。 - Zuiko Digital 14-54
ゴム自体が分解してバター状に溶ける。ここまで来ると拭き取りでは改善せず、交換が必要。 - Nikonの一部レンズ
ベタつきではなく「白化」や「硬化」が多い。これはEPDM寄りの配合による劣化。
ベタつき対策
- 軽度なら台所洗剤
油分(可塑剤)を界面活性剤で分散して落とす。ゴムへのダメージが少ない。 - 強めなら無水エタノール
表面を溶かしてリセット。ただしやりすぎると縮みや硬化のリスクあり。 - 仕上げにシリコンオイル
薄くなじませて保護とツヤ出し。 - 重度なら交換
ゴムそのものが溶けている場合は、交換用リングに替えるしかない。
まとめ
ピントリングのベタつきは「加水分解」だけでは説明できません。
実際には、
- 可塑剤がにじみ出す
- ポリウレタンが水分で分解する
- 紫外線や酸化も影響する
これらが重なって起こる現象なのです。
そして、規制によって安全な可塑剤に切り替わった今も、ベタつきそのものはなくなっていません。むしろ相溶性の問題でにじみやすい配合になっている場合もあります。
つまりベタつきは「材質の宿命」。設計上、操作感を優先した柔らかい配合が選ばれている以上、時間が経てば避けられない現象なのです。