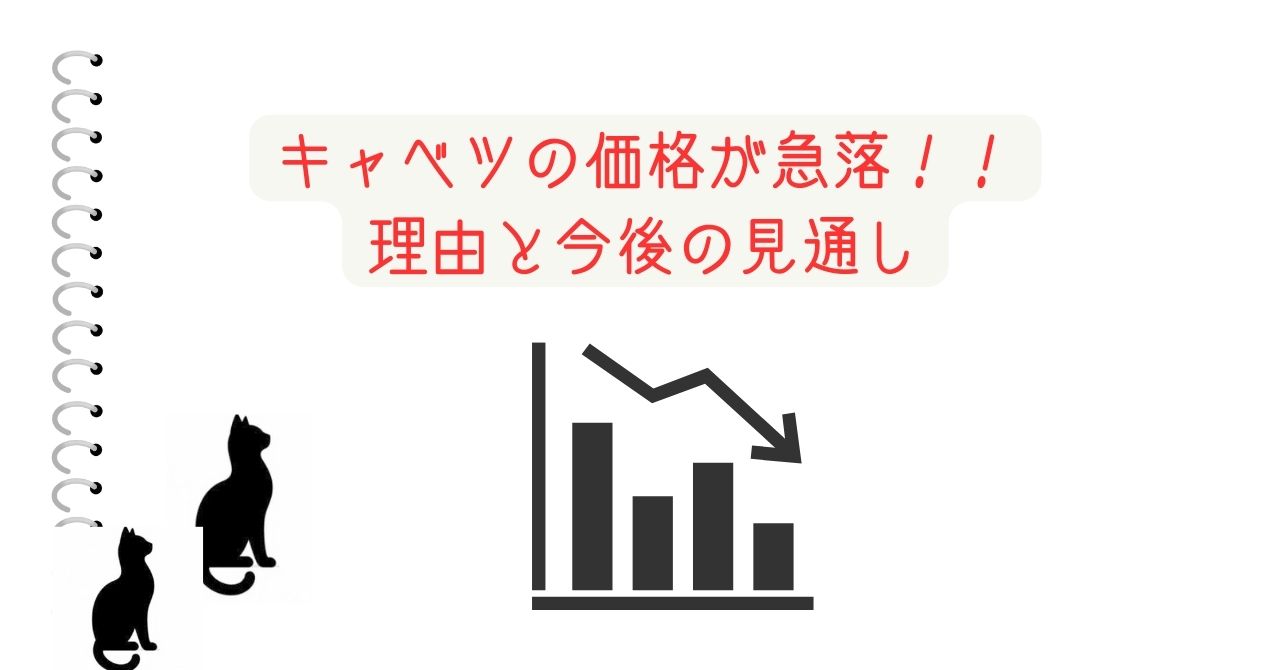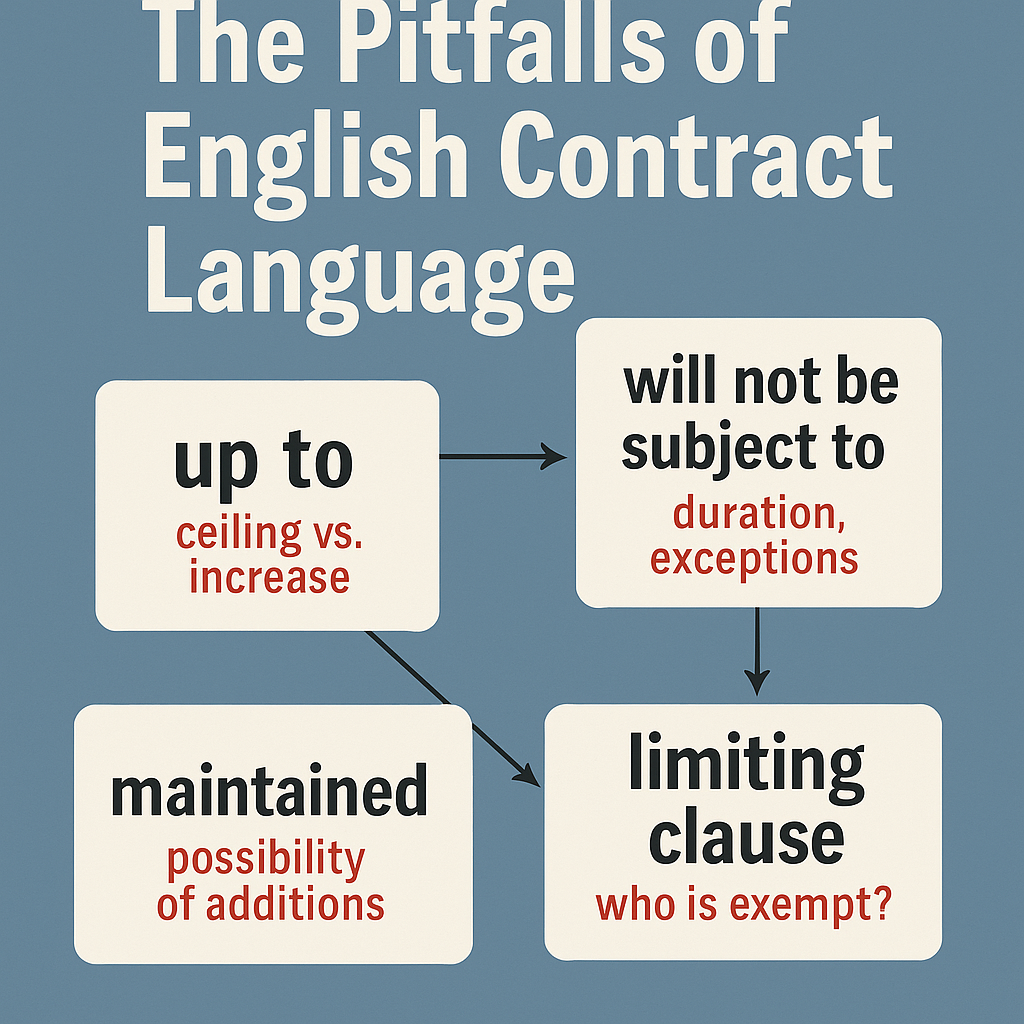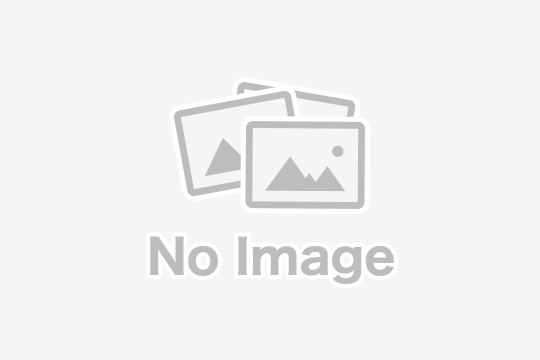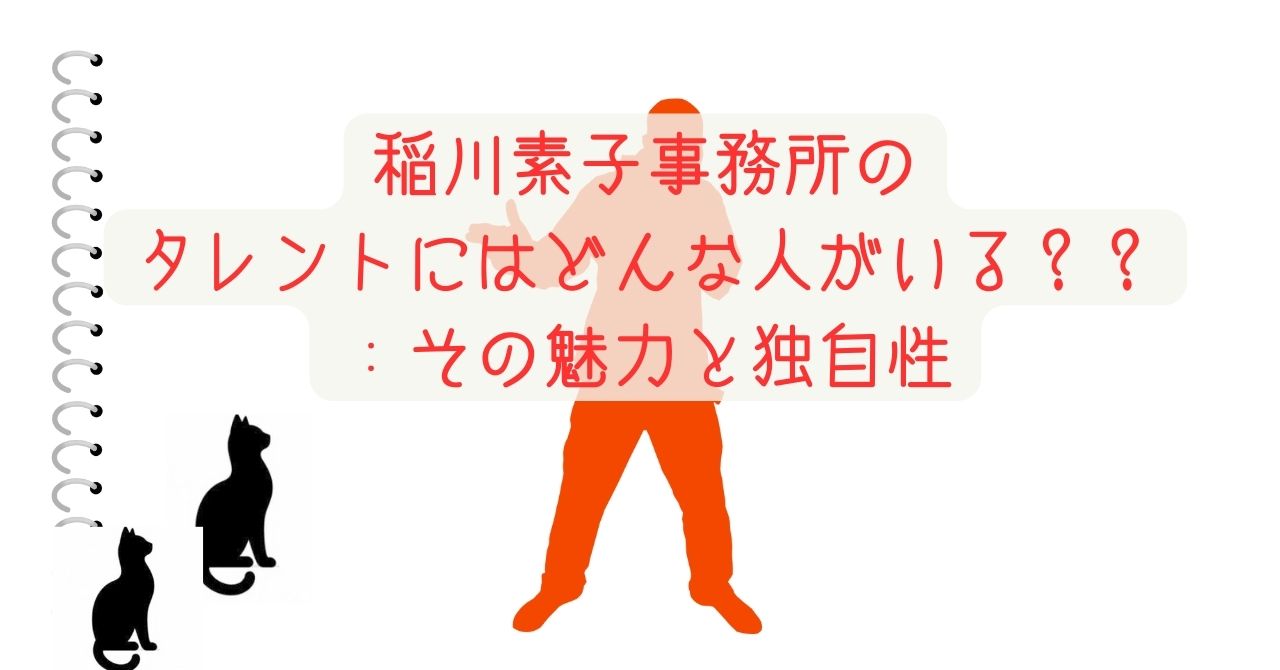不同意わいせつ事件で容疑者が「覚えていない」と言う…この言い訳は裁判で通用する?
この類のニュースに接すると、多くの人が強い憤りを感じるはずです。
それでも報道では「覚えていない」「そんなつもりじゃなかった」といった容疑者の言い訳が必ずといっていいほど出てきます。
でも、これって本当に通用するの? 結論から言うと、ほぼ通用しません。
よくある言い訳パターン
- 「記憶があいまいで覚えていない」
- 「そのためにやったわけじゃない」
- 「同意があったと思った」
なぜ通用しないの?
客観的な証拠が強いからです。
防犯カメラ、店内の移動履歴、レシート、位置情報。今は全部つながります。
特に今回のように睡眠薬を用意して混入した時点でアウト。
本来は医療用の薬ですが、他人に無断で飲ませれば実質的に「毒を盛る」行為です。
録画があるとどうなる?
映像は強力です。被害者の証言+映像で、言い訳は崩れますよね。
「覚えていない」は責任を免れません。行為は映像で再現できます。
裁判での扱われ方
否認やあいまいな供述は、信用性が低いと見られがちです。
量刑を少しでも軽く…という狙いにすぎない、と判断されることもあります。
なぜ言い訳が後を絶たないのか
それでも容疑者が同じような言い訳を繰り返すのには理由があります。
ひとつは心理的な防衛反応です。自分の行為を正面から認めると罪悪感や社会的非難に直面するため、無意識に責任をぼかそうとします。
もうひとつは裁判での戦略です。完全に認めれば量刑が重くなる可能性があるため、少しでも刑を軽くする狙いで「一部否認」を続けるケースがあります。
つまり、通用しないと分かっていても「自分を守りたい」という心理と「刑を軽くしたい」という打算が、こうした言い訳を生み続けているのです。
ここがポイント
- 薬を盛る行為そのものが違法で、事実上「毒を盛る」のと同じ。
- 「覚えていない」では責任は消えない。
- 映像や客観証拠がそろえば有罪認定に直結しやすい。
- 言い訳が繰り返されるのは、心理的防衛と量刑対策が背景にある。
まとめ
定番の言い訳は、今の証拠環境ではほとんど通用しませんよね。
睡眠薬を混入するのは「毒を盛る」と同じ。録画がある時点で、逃げ道はほぼありません。
それでも言い訳が後を絶たないのは、人間の心理と刑事戦略の表れにすぎないのです。