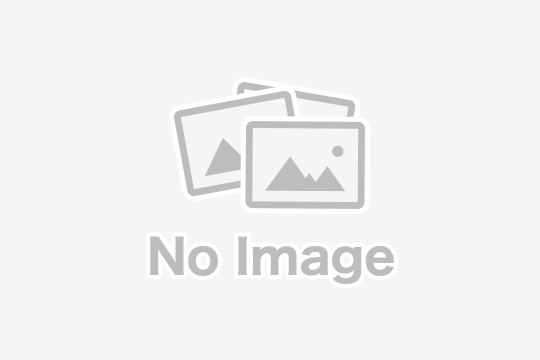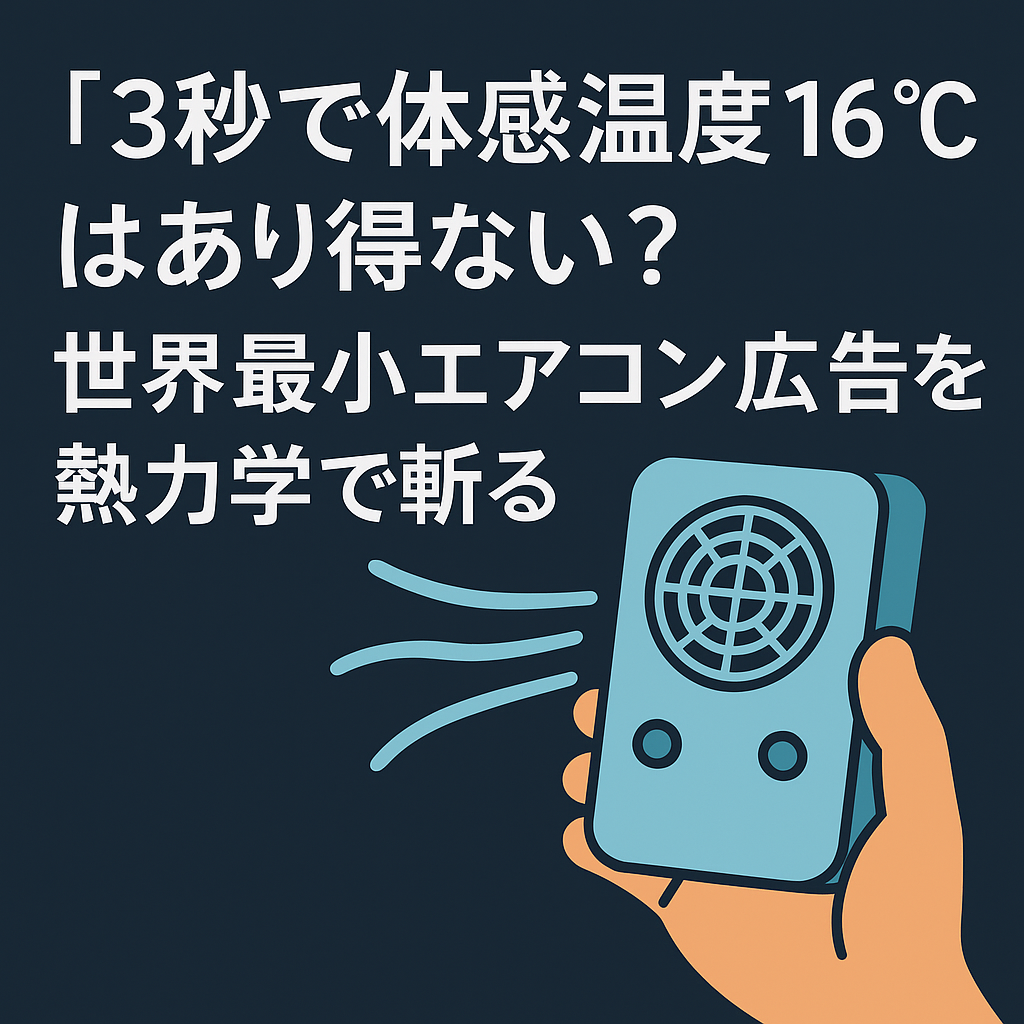政治資金ってどう集めて何に使うの?
政治活動をするにはお金が必要ですよね。選挙のポスターやビラ、事務所の運営、秘書の人件費など、すべて「政治資金」でまかなわれています。では、政治資金はどうやって集められて、何に使われているのでしょうか?
政治資金の集め方
政治資金の主な集め方は次のとおりです。
- 寄付(献金)
個人や企業・団体からのお金。ただし金額や方法には制限があり、外国人や外国企業からは受け取れません。 - 政治資金パーティー
パーティー券を売って資金を得る仕組み。実質的に企業・団体がまとめて購入するケースが多く、大きな収入源になっています。 - 政党交付金
国(税金)から毎年約320億円が政党に分配されます。議員数や得票数に応じて配られる仕組みです。 - その他
後援会の会費や機関紙の売上など。
使い道
集められた政治資金は、基本的に「政治活動」に限定して使われます。
- 秘書やスタッフの給料(人件費)
- 事務所の家賃や光熱費
- ポスター、チラシ、SNS広告などの広報活動
- 調査や会合、出張などの政治活動費
- 選挙運動費(ただしこれは公職選挙法でさらに厳しく規制あり)
生活費に使うことはできませんが、「政治活動の範囲」が曖昧で、不透明さが指摘されることもあります。
国からのお金と寄付の割合
実際には「税金」と「パーティー収入」が柱になっています。
例:自民党(2023年)
- 総収入:約491億円
- 政党交付金:約176億円(全体の36%)
- 政治資金パーティー収入:約198億円(40%)
- 企業・団体献金:約20億円
- 個人献金:約3億円
つまり、
- 国からの政党交付金:30〜40%
- パーティー収入:30〜40%
- 企業・団体+個人献金:10%前後
という構成になっています。
パーティー収入が批判される理由
政治資金パーティーは合法ですが、いくつかグレーな点があります。
- 企業献金の代替になっている
献金には上限があるけど、パーティー券購入は寄付扱いではないため、実質的に上限を超えた資金提供が可能。 - 透明性が低い
1回20万円以下の購入者は公開義務がないため、「誰がいくら出したか」が見えにくい。 - 見返りが疑われやすい
特定業界から多額の購入 → その業界に有利な政策、という構図が批判されやすい。
海外との比較
日本の仕組みを理解するには、海外と比べるとわかりやすいです。
- アメリカ
個人献金が中心で、小口寄付文化が根付いている。PACやSuper PACが巨額の資金を動かす。 - ドイツ
国からの政党助成金が中心。得票数に応じて配分され、公平性を重視。 - イギリス
国からの助成は少なく、個人献金や労働組合の支援が中心。政党の色が資金源に反映されやすい。
まとめ
日本の政治資金は「国からの税金(政党交付金)」と「政治資金パーティー収入」が大きな柱。海外のように「税金中心」や「個人献金中心」とは違い、両方を合わせた独特の仕組みになっています。その一方で、パーティー収入が企業献金の抜け道になっていると批判されることも多いんです。
政治資金の流れを知ることは、政治を理解する第一歩になりますよね。
------------<広告>------------