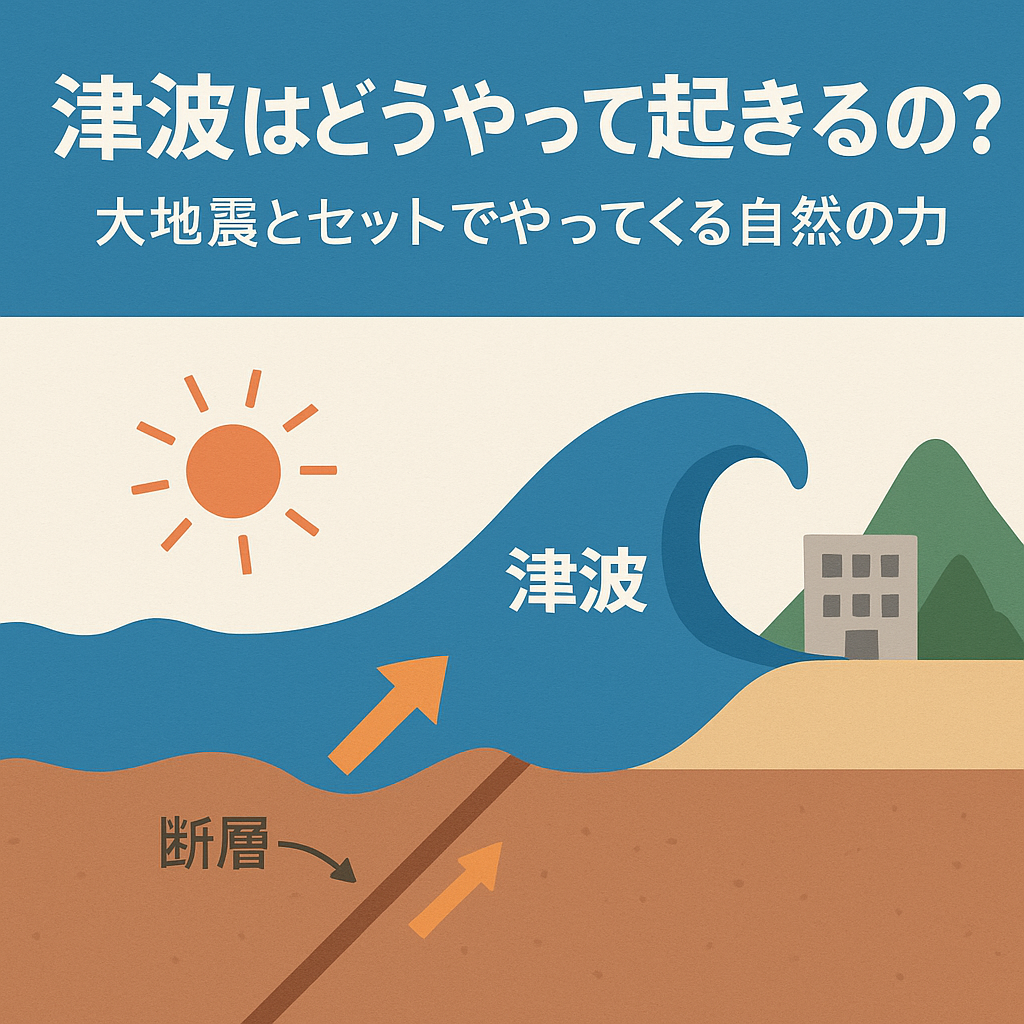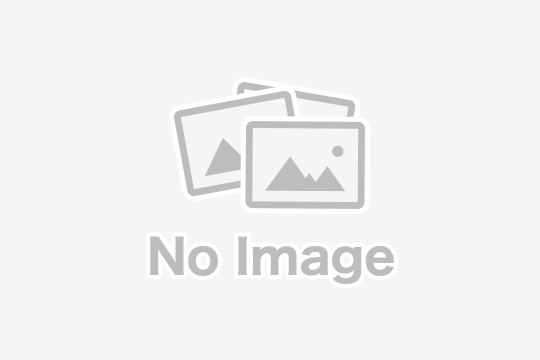記憶喪失はなぜ起こる?脳の仕組みからわかりやすく解説
ニュースでも「記憶喪失の男性が見つかった」という話題を見かけることがありますよね。記憶が突然失われるというのは、とても不思議で怖い現象です。この記事では、記憶喪失のきっかけや脳のメカニズムについて、わかりやすく整理してみます。
記憶喪失のきっかけ
- 強いストレスやトラウマ
心理的ショックで一時的に記憶が抜け落ちる「解離性健忘」。戦争体験や災害後にも見られます。 - 頭部外傷
交通事故や転倒で頭を打つと、直前・直後の出来事を忘れる「逆行性健忘」「前向性健忘」が起こることがあります。 - 脳血管障害やてんかん
「一過性全健忘(TGA)」と呼ばれ、数時間〜1日だけ記憶が抜け落ちるタイプです。 - アルコールや薬物
大量飲酒後の「ブラックアウト」や薬の副作用で記憶が記録されないことがあります。
脳のどの部分が関わるのか?
- 海馬:新しい記憶を作る中継所。障害があると新しいことを覚えられない。
- 扁桃体:恐怖や不安を司る。ストレスで過敏になると記憶の定着を妨げる。
- 前頭前野:記憶の検索や整理を担当。うまく働かないと「思い出す」ことができなくなる。
- 側頭葉:出来事の記憶を保存。損傷で過去の記憶が呼び出せなくなる。
タイプ別・脳の変化
- 一過性全健忘(TGA)
海馬の血流が一時的に低下。MRIで小さな異常が映ることも。 - 解離性健忘
器質的な損傷はなく、ストレスで前頭葉と海馬の連携が乱れる。 - 外傷性健忘
衝撃で側頭葉や海馬のニューロンが破壊され、記憶そのものが失われる。 - アルコール性健忘
海馬の神経伝達が阻害され、「記憶を保存するスイッチ」が切られる。
「忘れる」とは何か?
よく「記憶は消えるのではなく、アクセスできなくなる」と言われます。脳の中では、記憶は神経回路のパターン(エングラム)として残っているのです。
例えば図書館に本が並んでいても、検索カード(アクセス経路)がなければ本を見つけられませんよね。記憶喪失とは、この検索カードが一時的に失われた状態に近いのです。
アクセス障害の仕組み
- 前頭前野の機能低下:検索能力が落ち、思い出せなくなる。
- ストレスによる扁桃体の過敏化:危険な記憶を「封印」してしまう。
- 脳血流や伝達物質の乱れ:海馬が働かず、記憶が呼び出せなくなる。
実際の研究例
動物実験では、海馬の記憶回路を人工的にオフにすると記憶を失ったように見えますが、オンに戻すと再び思い出せることが確認されています。つまり「記憶は消えていなかった」ということです。
身近な「物忘れ」との関係
「最近物忘れが増えたな」「記憶力が落ちたかも」と感じること、ありませんか?これは病気というよりも、脳の「検索機能」が一時的に鈍っていることが多いのです。加齢やストレス、睡眠不足などで前頭前野や海馬の働きが弱まると、思い出したい情報にすぐアクセスできなくなります。
記憶喪失とは違って、日常の物忘れは一時的で軽度なものです。でも「記憶は残っているのにアクセスが難しい」という点では、どちらも共通しています。
まとめ
記憶喪失は「脳の損傷」で起こることもあれば、「心の防御反応」で起こることもあります。忘れるのではなく、アクセス経路を失うことで思い出せなくなるケースが多いのです。
一方で、私たちが日常で感じる物忘れも同じメカニズムが関係しています。つまり「記憶は残っているのに思い出せない」現象は、誰にでも起こり得ることなんですね。