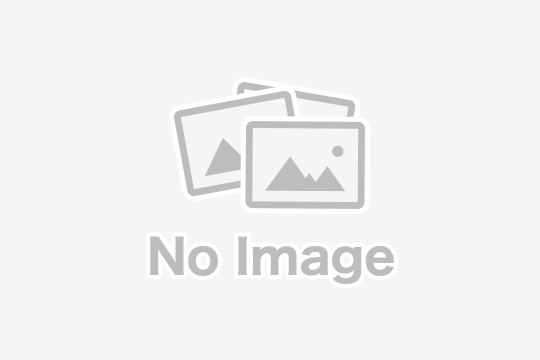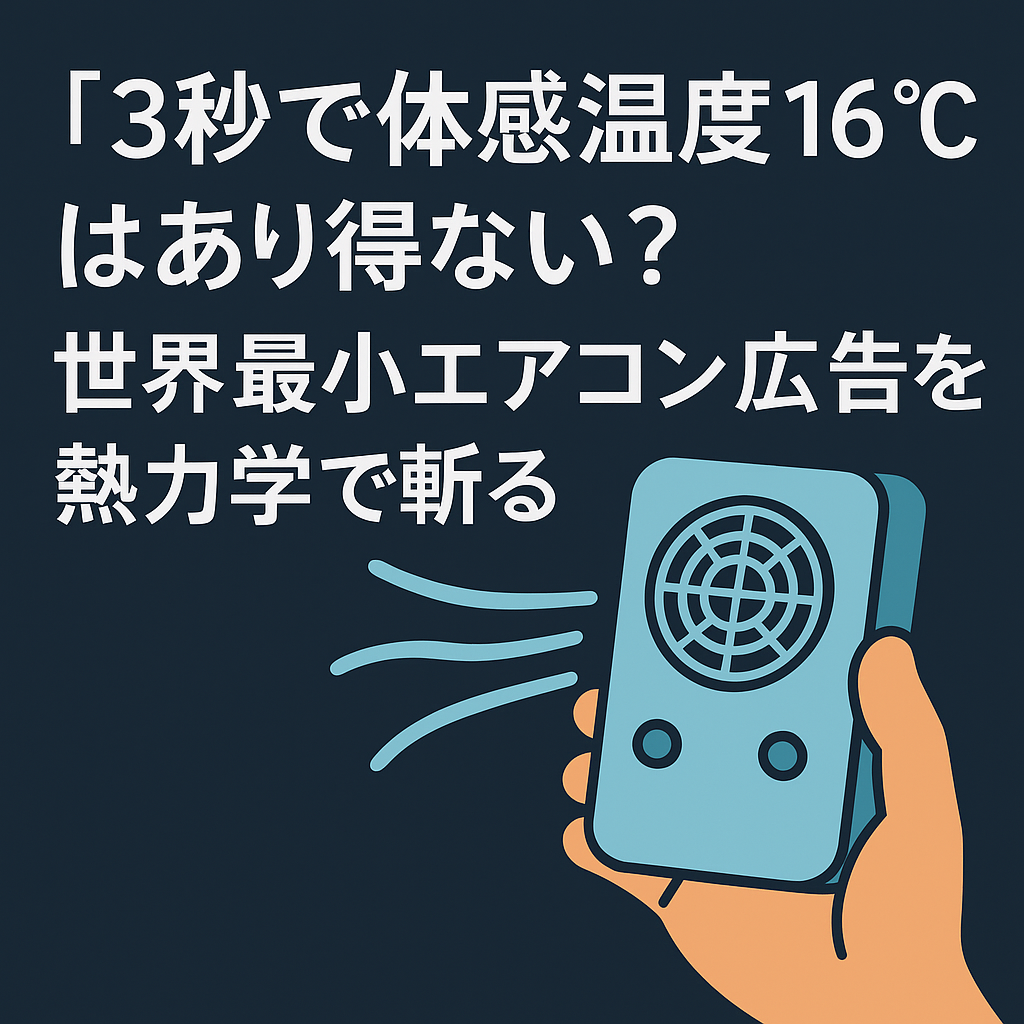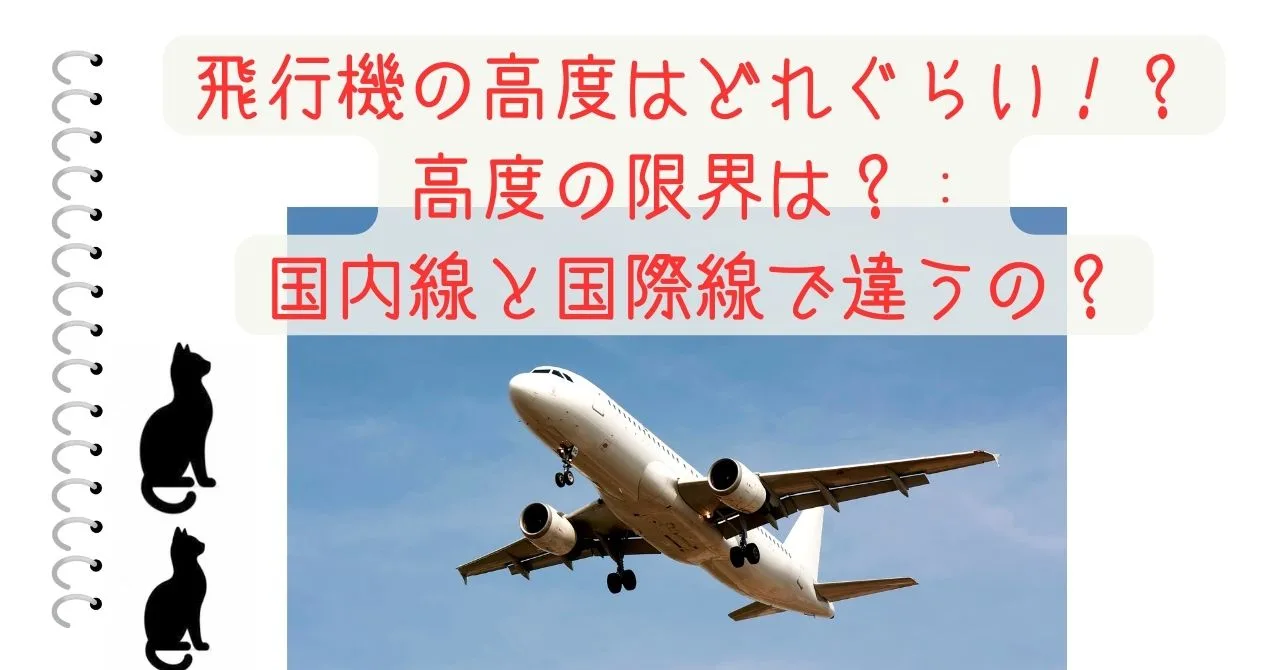もし言葉がなかったら…思考はどうなる?言語が担う「頭の中の地図」の役割
もし私たちが言葉をまったく持たなかったら、どんなふうに考えるのでしょうか。
痛みや喜びを感じたり、簡単な予測を立てることはできますが、抽象的な概念や複雑な計画になると話は別です。
言語は単なる伝達の道具ではなく、経験や情報を整理する“地図”のような役割を果たしています。
本記事では、言語が思考に与える影響を、わかりやすい事例とたとえ話で解説します。
言語がなかった場合思考は?
言語を習得しなかった場合でも、ある程度の「思考」はできます。
ただし、その思考の質や範囲はかなり制限されます。
1. 言語なしでも可能な思考
- 感覚・感情の処理
痛み、喜び、恐怖といった感情は言語がなくても感じられます。
動物や乳児が危険を避けたり、快適さを求めたりできるのはこのためです。 - パターン認識・予測
「この行動をすると危険がある」と学習し、次の行動を選ぶことも可能です。
これは言語というより経験と脳の連想能力に依存します。 - イメージ思考
映像・音・匂いといった感覚記憶を元に頭の中でシミュレーションすることはできます。
例:木の実を見て「食べられる」と直感する。
2. 言語がないと思考が制限される部分
- 抽象的な概念の操作が難しい
「正義」「時間」「もしも」といった、感覚に直接ない概念は整理が難しくなります。 - 複雑な計画立案が困難
言語は情報を順序立てて保持・組み替えるための強力なツール。
言語なしだと、同時に扱える情報量が減ります。 - 自己省察の制限
自分の感情や行動の理由を「言葉」にできないため、内面を深く分析しにくくなります。
3. 実際の例
- ろう者の事例
生まれつき聴覚障害があり、幼少期に手話などの言語習得機会がなかった人は、後から言語を覚えると抽象的な思考が急速に広がることが報告されています。 - 動物の知能
チンパンジーやイルカは複雑な問題解決はできますが、人間のような高度な哲学や科学は生み出せません。
これは言語による情報構造化がないためです。
言語は情報構造化の役割もはたしている
言語が情報を構造化する仕組み
- ラベル付け
言葉を使うことで、バラバラな経験や感覚に「名前」を付けられます。
例:バラの花 → 「赤い」「香りがある」「トゲがある」と分けて認識。 - 順序立て
文法や語順で、出来事や理由を時系列や因果関係で並べられます。
例:「雨が降ったので川が増水した」 - 抽象化
具体的な事例をまとめて共通点を引き出せます。
例:「リンゴ」「バナナ」「ミカン」→「果物」という上位概念。
言語がない場合の思考の特徴
- イメージや感情は直感的に浮かぶが、それを細かく分類・比較しにくい
- 原因や結果の関係を複数同時に扱うのが苦手
- 「もし~なら」という仮想の世界を安定して保持しづらい
言語による情報構造化」を、地図と土地の関係にたとえて説明

「言語=地図、現実世界=土地」というたとえで説明しますね。
1. 言語は地図のようなもの
現実世界(経験や感覚)は、広大で複雑な「土地」です。
そのままだと広すぎて、どこに何があるか整理できません。
そこで**言語という“地図”**を使えば、場所(情報)の位置や関係を分かりやすく整理できます。
2. 地図があるとできること
- 位置の特定(ラベル付け)
地図上で「ここは山」「ここは川」と名前をつける → 言語で「赤い花」「冷たい水」と名前をつける - 道順の記録(順序立て)
地図で移動ルートを描く → 言語で「Aが起きたからBが起きた」と因果関係を整理 - 俯瞰と抽象化
地図で広い範囲をまとめて見られる → 言語で「果物」「道具」など上位の概念にまとめる
3. 地図(言語)がないとどうなるか
- 現実の景色(感覚や経験)は見えるが、道筋や位置関係を整理できない
- 同じ景色でも過去と現在を比較しづらい
- 新しい道(仮説)を想像するのが難しい
要するに、**言語は頭の中の“情報地図”**で、
それがあるからこそ私たちは、経験を整理し、他人と共有し、未来を計画できるんですよね。
まとめ
言語なしでも「感じる」「覚える」「単純な予測をする」思考は可能です。
しかし、言語は思考の“作業机”のようなもので、複雑で抽象的な思考はほぼ不可能になります